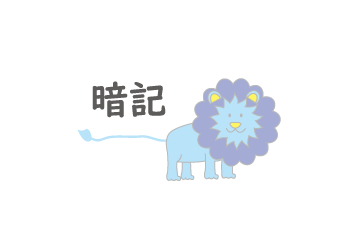1章の暗記特訓ページだよ
暗記特訓のやり方のページを読んでから特訓してね
暗記特訓
■医薬品の本質
医薬品は人体にとっては【A】であるため、また人体に及ぼす作用は複雑で多岐にわたり、すべてが【B】ため、有益な効果(薬効)のみをもたらすとは限らず、好ましくない反応(【C】)を生じる場合もある。
A異物 B解明されていない C副作用
■医薬品の効果とリスク1
医薬品の効果とリスクは、用量と作用【A】との関係で表現される用量 – 反応関係に基づいて評価される。
A強度
■医薬品の効果とリスク2
投与量と効果又は毒性の関係は薬物用量を増加させるに伴い無作用量から【A】を経て治療量に至る。治療量上限を超えると【B】となり、最小致死量を経て致死量に至る。
A最小有効量 B中毒量
■新規開発医薬品承認前のリスク評価
医薬品の安全性に関する非臨床試験は【A】に準拠して、薬効・薬理試験、一般薬理作用試験が行われ、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って毒性試験が実施される。
ヒトを対象とした臨床試験(治験)は、【B】に準拠して行われる。
A:GLP B:GCP
■製造販売後の調査・試験
医薬品に対しては製造販売後の調査及び試験の実施基準として【A】 と、製造販売後安全管理基準として【B】が制定されている。
医薬品と食品では、【C】の方が安全性基準が厳しい。
A:GPSP B:GVP C:医薬品
■副作用の分類
医薬品の副作用は、薬理作用によるものと、【A】(過敏反応)によるものに大別することができる。
Aアレルギー
■副作用の定義
世界保健機関(WHO) の定義によれば、医薬品の副作用とは、「疾病の【A】、診断、治療のため、又は身体の機能を 【B】するために、人に【C】量で発現する医薬品の有害かつ【D】反応」 とされている。
A予防 B正常化 C通常用いられる量 D意図しない
■副作用の扱い
主作用以外の反応であっても、特段の不都合を生じないものは、通常、副作用として【A】が、好ましくないもの(有害事象)については、一般に副作用という。副作用の程度は、軽微なものから重大なものまで様々である。
A扱われない
■副作用の回避
一般用医薬品は、【A】な疾病に伴う症状の改善等を図るものであり、【B】が自らの判断で使用するものであることから、通常は、その使用を【C】することによる不利益よりも、重大な副作用を回避することが優先される。
A軽度 B一般の生活者 C中断
■適正な選択と使用
医薬品は、【A】上のリスクを伴うものであり、適切な医薬品が選択され、適正な使用がなされなければ、有害事象を招く危険性がある。
A保健衛生
■薬物乱用
適正に使用される限りは安全で有効な医薬品であっても、乱用された場合には【A】を生じることがある。
A薬物依存
■青少年と薬物乱用
一般用医薬品にも【A】性・【B】性のある成分を含むものがあり、乱用されることがある。青少年は薬物乱用の危険性についての認識や理解が必ずしも十分でなく、興味本位で乱用することがあるので注意が必要である。
A習慣 B依存
■アルコールの影響
酒類(アルコール)は主に【A】で代謝されるため、酒類をよく摂取する者は【A】の代謝機能が【B】まっていることが多く、アセトアミノフェンは通常よりも代謝【C】なり、【D】ことがある。
A肝臓 B高 Cされやすく D十分な薬効が得られなくなる
■医薬品の吸収率
小児は大人と比べて身体の大きさに対して腸が【A】いため、服用した医薬品の吸収率が【B】い。また、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が【C】に達しやすいため、中枢神経系に影響を与える医薬品で副作用を起こしやすい。
A長 B高 C脳
■子どもや高齢者の年齢
新生児 【A】週未満
乳児 【B】歳未満
幼児 【C】歳未満
小児 【D】歳未満
高齢者 【E】歳以上
A 4 B 1 C 7 D 15 E 65
■医薬品の代謝・排泄
小児は肝臓や腎臓の機能が【A】なため、医薬品の成分の代謝・排泄に時間が【B】、作用が強く出すぎたり、副作用がより強く出ることがある。
A 未発達 Bかかり
■生理機能の衰えと医薬品
一般に高齢者は【A】が衰えつつあり、特に肝臓や腎臓の機能が低下していると、医薬品の作用が強く現れやすく、若年時と比べて副作用を生じるリスクが高くなる。ただし、基礎体力や生理機能の衰えの度合いは【B】が大きく、年齢のみから判断するのは難しい。
A生理機能 B個人差
■高齢者への配慮
高齢者は、嚥下障害により内服薬を喉に詰まらせたり、医薬品の副作用により口渇を生じて飲食中に【A】を誘発しやすくなる。
A誤嚥(ごえん)
■安全性の評価
一般用医薬品においては、多くの場合、妊婦が使用した場合における安全性に関する評価が困難であるため、妊婦の使用については「【A】」としているものが多い。
A相談すること
■危険性
ビタミン【A】含有製剤は、妊娠前後の一定期間に通常の用量を超えて摂取すると、胎児に【B】を起こす危険性が高まる。
A:A B:先天異常
■副作用
インターフェロン製剤で治療を受けている人が、小柴胡湯の配合されたかぜ薬を使用すると、【A】を起こすおそれがある。
A間質性肺炎
■プラセボ効果とは
医薬品を使用したとき、【A】的または【B】的に、【C】作用によらない作用を生じることをプラセボ効果という。
A結果 B偶発 C薬理
■期限
表示されている「【A】期限」は、【B】状態で保管された場合に品質が保持される期限である。
A使用 B未開封
■一般用医薬品の使用目的
一般用医薬品は、日常において、生活者が自らの疾病の【A】、【B】 をすることなどを目的としている。
A治療 B予防
■一般用医薬品の役割
一般用医薬品の役割には、次の6つがある。
① 【A】な疾病に伴う症状の改善
② 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の【B】
③ 生活の質(【C】)の改善・向上
④ 健康状態の自己【D】
⑤ 健康の維持・増進
⑥ その他【E】(衛生害虫の防除、殺菌消毒等)
A軽度 B予防 C:QOL D検査 E保健衛生
■セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、【A】な身体の不調は自分で手当てする」ことである。(WHO)
A軽度
練習問題

暗記はできたかな?
ここからは練習問題だよ。最後の方は薬害訴訟が多めになってるよ。
問 1 医薬品の本質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
| a | 医薬品は、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されるなど、有用性が認められたものであり、保健衛生上のリスクは伴わない。 |
|---|---|
| b | 一般用医薬品については、医療用医薬品と比較すれば保健衛生上のリスクは相対的に低いため、リスク区分の見直しが行われることはない。 |
| c | 一般用医薬品の販売には、専門家の関与は必要ない。 |
| d | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)では、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならないと定めている。 |
| a b c d | |
| 1 | 正 正 誤 誤 |
| 2 | 正 誤 誤 正 |
| 3 | 誤 誤 誤 正 |
| 4 | 誤 正 正 正 |
| 5 | 正 誤 正 誤 |
【正解3】
a× 保健衛生上のリスクを伴う
b× リスク区分の見直しが行われる
c× 専門家の関与が必要である
d〇
問 2 医薬品のリスク評価に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
| 1 | 医薬品の効果とリスクは、用量と作用強度の関係(用量-反応関係)に基づいて評価される。 |
|---|---|
| 2 | 動物実験により求められる50%致死量(LD50)は、薬物の毒性の指標として用いられる。 |
| 3 | 新規に開発される医薬品のリスク評価は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準である Good Clinical Practice(GCP)の他に、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って、毒性試験が厳格に実施されている。 |
| 4 | 医薬品の製造販売後安全管理の基準として Good Vigilance Practice(GVP)が制定されている。 |
【正解3】
Good Clinical Practice(GCP)ではない。正しくはGood Laboratory Practice(GLP)。
問 3 いわゆる健康食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
| a | 古くから特定の食品摂取と健康増進との関連は関心を持たれてきた。 |
|---|---|
| b | 「特定保健用食品」は、個別に特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。 |
| c | 健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じることがある。 |
| d | 健康食品は、カプセル、錠剤等の医薬品と類似した形状では販売されていない。 |
| a b c d | |
| 1 | 正 誤 誤 誤 |
| 2 | 誤 誤 正 正 |
| 3 | 誤 正 誤 正 |
| 4 | 誤 正 正 誤 |
| 5 | 正 正 正 誤 |
【正解5】
a〇
b〇
c〇
d×カプセル・錠剤等の医薬品と類似した形状の健康食品も販売されている
問 4 薬理作用やアレルギーに関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
| a | 医薬品の有効成分である薬物が生体の生理機能に影響を与えることを薬理作用という。 |
|---|---|
| b | アレルギーは、医薬品の薬理作用等とは関係なく起こり得るものである。 |
| c | 医薬品にアレルギーを起こしたことがない人は、医薬品がアレルギーを引き起こす原因物質(アレルゲン)になることはない。 |
| d | 医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作られているものもあるが、製造工程で除去されるため、それらに対するアレルギーがある人でも使用を避ける必要はない。 |
1(a,b)
2(a,c)
3(a,d)
4(b,c)
5(b,d)
【正解1】
a〇
b〇
c×普段は医薬品にアレルギーを起こしたことがない人でも、体調によっては医薬品がアレルゲンになることがある。
d×医薬品の中には、鶏卵や牛乳等を原材料として作られているものがあるため、それらに対するアレルギーがある人は使用を避けなければならない場合もある。
問 5 医薬品の副作用に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。
| ア | 世界保健機関(WHO)の定義では、医薬品の副作用とは、「疾病の予防、診断、治療のため、又は身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされている。 |
|---|---|
| イ | アレルギーは、一般的にあらゆる物質によって起こり得るものであるため、医薬品の薬理作用とは関係なく起こり得るものである。 |
| ウ | アレルギーは、外用薬では引き起こされることはない。 |
| エ | 一般用医薬品は、軽度な疾病に伴う症状の改善等を図るものであり、その使用による重大な副作用を回避するよりも、使用の中断による不利益を避けることを優先するべきである。 |
| 1 | ア、イ |
|---|---|
| 2 | ア、ウ |
| 3 | イ、エ |
| 4 | ウ、エ |
【正解1】
ア○
イ○
ウ× 外用薬でも引き起こされることがある
エ× 一般用医薬品は、使用を中断することによる不利益よりも、重大な副作用を回避することが優先される
問 6 医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
| a | 副作用は、眠気や口渇等の比較的よく見られるものから、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生じる重大なものまで様々である。 |
|---|---|
| b | 医薬品が人体に及ぼす作用は、すべてが解明されているわけではないので、十分に注意して適正に使用された場合であっても、副作用が生じることがある。 |
| c | 副作用の状況次第では、医薬品の販売等に従事する専門家は購入者等に対して、速やかに適切な医療機関を受診するよう勧奨する必要がある。 |
| d | 副作用は、容易に異変を自覚できるものがほとんどであり、継続して使用する場合は、特段の異常が感じられる場合のみ医療機関を受診するよう、医薬品の販売等に従事する専門家から促すことが重要である。 |
| a b c d | |
| 1 | 正 誤 誤 正 |
| 2 | 正 正 誤 正 |
| 3 | 正 正 正 誤 |
| 4 | 誤 正 正 正 |
| 5 | 誤 誤 正 誤 |
【正解3】
a〇
b〇
c〇
d×異変を自覚できるものばかりではなく、明確な自覚症状として現れないこともある。特段の異常が「感じられなくても」医療機関を受診するよう、医薬品の販売等に従事する専門家から促すことが重要である。
問 7 医薬品の不適正な使用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
| a | 一般用医薬品には習慣性・依存性がある成分を含んでいるものがある。 |
|---|---|
| b | 青少年は、薬物乱用の危険性に関する認識や理解が十分であり、特別な注意は必要ない。 |
| c | 医薬品の販売等に従事する専門家は、必要以上に大量購入や頻回購入を試みる者等に、積極的に事情を尋ね、状況によっては販売を差し控えるなどの対応をすることが望ましい。 |
| d | 薬物依存は、医薬品を乱用した場合に生じることがあり、連続的、あるいは周期的に摂取することへの欲求を常に伴っている行動等に特徴づけられる精神的・身体的な状態のことをいう。 |
| a b c d | |
| 1 | 誤 誤 正 誤 |
| 2 | 正 正 誤 誤 |
| 3 | 正 誤 正 正 |
| 4 | 誤 正 正 正 |
| 5 | 誤 誤 誤 正 |
【正解3】
a〇
b×青少年は、薬物乱用の危険性に関する認識や理解が「必ずしも十分でなく、注意が必要である」。
c〇
d〇
問8 以下の医薬品の副作用に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
世 界 保 健 機 関 ( W H O ) の 定 義 に よ れ ば 、 医 薬 品 の 副 作 用 と は 、 「 疾 病 の 予 防 、( a )、治療のため、又は身体の機能を正常化するために、人に( b )量で発現する医薬品の有害かつ( c )反応」とされている。
| 1 | a診断 b用いられる最小 c意図しない |
|---|---|
| 2 | a検査 b通常用いられる c予測できる |
| 3 | a検査 b用いられる最小 c予測できる |
| 4 | a診断 b通常用いられる c予測できる |
| 5 | a診断 b通常用いられる c意図しない |
【正解5】
問 9 医薬品及び食品に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。
酒類(アルコール)は、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがある。アルコールは、主として肝臓で代謝されるため、酒類(アルコール)をよく摂取する者では、肝臓の代謝機能が( ア )なっていることが多い。その結果、肝臓で代謝されるアセトアミノフェンなどでは、通常よりも代謝され( イ )なっているため体内から医薬品が( ウ )消失する傾向がある。
| 1 | ア 低く イ やすく ウ 遅く |
|---|---|
| 2 | ア 低く イ にくく ウ 速く |
| 3 | ア 高く イ やすく ウ 速く |
| 4 | ア 高く イ にくく ウ 速く |
| 5 | ア 高く イ にくく ウ 遅く |
【正解3】
問 10 小児への医薬品の使用に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
| a | 5歳未満の幼児に使用される錠剤やカプセル剤などの医薬品では、服用時に喉につかえやすいので注意するよう添付文書に記載されている。 |
|---|---|
| b | 「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」において、新生児とは、おおよその目安として生後4週未満をいう。 |
| c | 小児は腎臓の機能が未発達であるため、医薬品の成分の排泄に要する時間が短く、作用が弱くなることがある。 |
| d | 小児は、大人と比べて身体の大きさに対して腸が短いため、服用した医薬品の吸収率が相対的に低く、期待する効果が得られない場合がある。 |
| a b c d | |
| 1 | 正 正 誤 誤 |
| 2 | 正 正 誤 正 |
| 3 | 正 誤 誤 誤 |
| 4 | 誤 誤 正 正 |
| 5 | 誤 誤 正 誤 |
【正解1】
a〇
b〇
c×腎臓の機能が未発達であるため、医薬品の成分の排泄に要する時間が長くかかり、作用や副作用が強く出ることがある。
d×大人と比べて身体の大きさに対して腸が長いため、服用した医薬品の吸収率が相対的に高い。
問 11 高齢者に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。
| a | 「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」(平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添)は、おおよその目安として75歳以上を「高齢者」としている。 |
|---|---|
| b | 年齢のみから、一概にどの程度、副作用のリスクが増大しているかを判断することは難しい。 |
| c | 一般に生理機能が衰えつつあり、特に、肝臓や腎臓の機能が低下していると医薬品の作用が現れにくくなる。 |
| d | 喉の筋肉が衰えて飲食物を飲み込む力が弱まっている(嚥下障害)場合があり、内服薬を使用する際に喉に詰まらせやすい。 |
1(a、b)
2(a、c)
3(b、d)
4(c、d)
【正解3】
a× 65歳以上
b〇
c×一般に生理機能が衰えつつあり、特に、肝臓や腎臓の機能が低下していると医薬品の作用が「強く現れやすい」。
d〇
問 12 妊婦又は妊娠していると思われる女性に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
| a | 一般用医薬品では、多くの場合、妊婦が使用した場合における安全性に関する評価が困難であるため、妊婦の使用については「相談すること」としているものが多い。 |
|---|---|
| b | 便秘薬は、配合成分やその用量によっては、流産や早産を誘発するおそれがあるため、十分注意して適正に使用するか、又は使用そのものを避ける必要がある。 |
| c | ビタミンB2含有製剤は、妊娠前後の一定期間に通常の用量を超えて摂取すると胎児に先天異常を起こす危険性が高まる。 |
| d | 胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらない仕組みとして、血液-胎盤関門がある。 |
| a b c d | |
| 1 | 誤 正 正 誤 |
| 2 | 正 正 誤 正 |
| 3 | 誤 正 誤 誤 |
| 4 | 正 誤 正 誤 |
| 5 | 誤 誤 正 正 |
【正解2】
a〇
b〇
c× ビタミンB2ではなくビタミンA
d〇
問 13 プラセボ効果に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
| a | 医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用による作用を生じることをプラセボ効果という。 |
|---|---|
| b | プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には、望ましいもの(効果)と不都合なもの(副作用)がある。 |
| c | プラセボ効果は、主観的な変化と客観的に測定可能な変化が、確実に現れる。 |
| d | プラセボ効果は、時間経過による自然発生的な変化(自然緩解など)が関与して生じる場合があると考えられる。 |
| a b c d | |
| 1 | 正 誤 正 正 |
| 2 | 正 正 正 誤 |
| 3 | 正 正 誤 誤 |
| 4 | 誤 正 誤 正 |
| 5 | 誤 誤 正 正 |
【正解4】
a×結果的又は偶発的に薬理作用に「よらない」作用を生じることをプラセボ効果という。
b〇
c×主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として「現れることもあるが、不確実である」。
d〇
問 14 一般用医薬品の定義に関する次の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
一般用医薬品は、医薬品医療機器等法第4条第5項第4号において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、( b )その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(( c )を除く。)」と定義されている。
| 1 | a著しくない b薬剤師 c処方箋医薬品 |
|---|---|
| 2 | a緩和な b医師 c要指導医薬品 |
| 3 | a著しくない b薬剤師 c要指導医薬品 |
| 4 | a著しくない b医師 c処方箋医薬品 |
| 5 | a緩和な b薬剤師 c要指導医薬品 |
【正解3】
問 15 一般用医薬品の役割に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
| a | 健康状態の自己検査 |
|---|---|
| b | 重度な疾病に伴う症状の改善 |
| c | 生活の質(QOL)の改善・向上 |
| d | 認知機能の低下予防 |
| a b c d | |
| 1 | 正 正 正 正 |
| 2 | 正 正 誤 正 |
| 3 | 正 誤 正 誤 |
| 4 | 誤 正 正 正 |
| 5 | 誤 誤 正 正 |
【正解3】
a〇
b×「重度な」ではなく「軽度な」
c〇
d×認知機能の低下予防ではなく、「健康の維持・増進」。
問 16 セルフメディケーション等に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
| a | 医薬品の販売等に従事する専門家は、セルフメディケーションを適切に支援していくことが期待されているため、情報提供は必ず医薬品の販売に結び付けるべきである。 |
|---|---|
| b | 世界保健機関(WHO)によれば、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされている。 |
| c | 体の不調について、一般用医薬品を使用して対処した場合であっても、一定期間使用しても症状の改善がみられないときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。 |
| d | 高熱や激しい腹痛がある場合など、症状が重いときに、一般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処といえる。 |
- 1(a,b)
- 2(a,c)
- 3(a,d)
- 4(b,c)
- 5(b,d)
【正解4】
a×「必ずしも医薬品の販売に結びつける」のではなく、状況に応じて受診勧奨や、医薬品の使用によらない対処を勧めるなどが適切な場合がある。
b〇
c〇
d×症状が「重いとき」は、医療機関へ受診したほうがよい。一般用医薬品の役割は「軽度な疾病に伴う症状の改善」である。
問 17 適切な医薬品選択と受診勧奨に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
| 1 | 一般用医薬品の販売等に従事する専門家は、購入者等に対して常に科学的な根拠に基づいた正確な情報提供を行い、セルフメディケーションを適切に支援していくことが期待されている。 |
|---|---|
| 2 | 軽度の症状について一般用医薬品を使用して対処した場合であっても、一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。 |
| 3 | 乳幼児や妊婦では、通常の成人の場合に比べ、一般用医薬品で対処可能な範囲は限られる。 |
| 4 | 一般用医薬品には、使用してもドーピングに該当する成分を含んだものはない。 |
【正解4】
1〇
2〇
3〇
4×一般用医薬品の成分の中には、使用すればドーピングに該当するものもあるため、スポーツ競技者から相談があった場合は、薬剤師などへの確認が必要である。